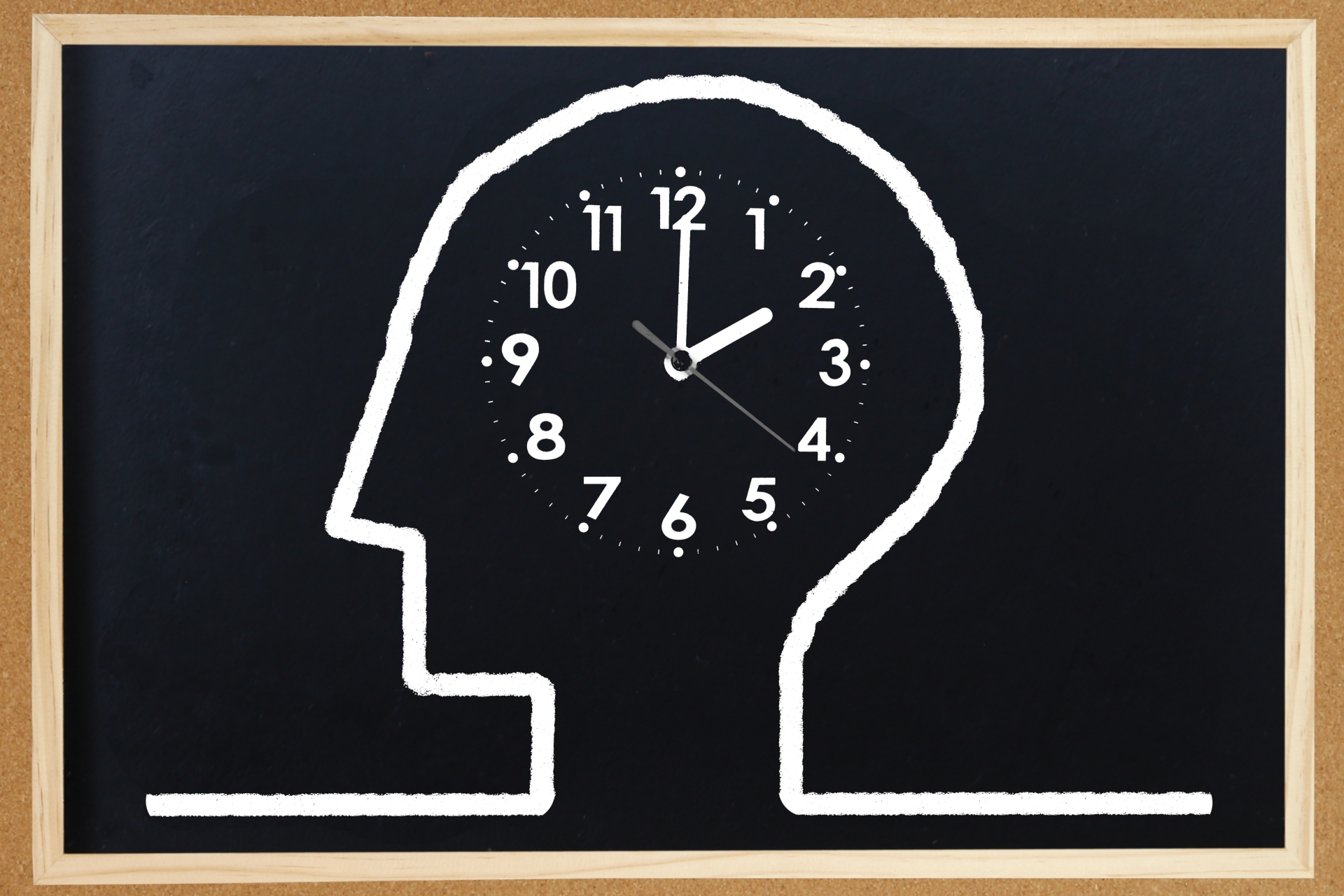体内にアルコールが吸収される仕組み
まずは、体内にアルコールが吸収される仕組みについて知っておきましょう。口から入ったアルコールは、肝臓で処理されます。アルコールは、ADH(アルコール脱水素酵素)やMEOS(ミクロゾームエタノール酸化系)によって分解され、アセトアルデヒドとなります。アセトアルデヒドは、飲み過ぎた後に起きる頭痛や動悸などの原因だとされています。
そして、肝臓内のALDH(アルデヒド脱水素酵素)によって酢酸へ分解され、最終的に水と二酸化炭素へと分解されます。それらは尿や汗、呼気などに含まれて体外へ排出されるのです。
アルコールが抜ける時間の目安
体がアルコールを代謝するのにかかる時間には個人差があります。関連する要素は、体質や体重、体格、年齢、性別などです。通常、お酒に強いタイプの男性は、飲酒から4時間程度はアルコールが体内に残るとされています。女性や高齢者、お酒に弱い人の場合、飲酒から5時間程度はアルコールが残るといえるでしょう。
お酒が身体から抜けるまでの時間について
お酒が身体から抜けるまでの時間については、以下の計算式で算出できます。
純アルコール量(g)÷(体重×0.1)=アルコール処理に要する時間
例えば、純アルコール量20gで体重60kgの場合は、次のように計算します。
純アルコール量20g÷(60kg×0.1)=約3.3時間(約3時間23分)
純アルコール20gは、アルコール度数5%のビール500mlに相当します。
純アルコール量(g)÷(体重×0.1)=アルコール処理に要する時間
例えば、純アルコール量20gで体重60kgの場合は、次のように計算します。
純アルコール量20g÷(60kg×0.1)=約3.3時間(約3時間23分)
純アルコール20gは、アルコール度数5%のビール500mlに相当します。
車の運転は何時間後からできる?
車の運転が何時間後からできるのかを考える際は、お酒のアルコール量を算出し、それをアルコールが身体から抜けるまでの時間を求める計算式にあてはめましょう。アルコール量は、お酒の量や種類で大きく異なります。代表的なお酒のアルコール量について詳しく見ていきましょう。
ビール
広く親しまれているビールは、180mlで純アルコール約7gです。比較的アルコール量が少ないのですが、何杯も飲む場合は注意が必要です。
ワイン
ワインは、ワイングラス120mlで純アルコール約12gです。ビールよりも格段に多い点に注意が必要です。
ウイスキー
ウイスキーは、水割りやお湯割りで飲むことが多いでしょう。シングル水割り(原酒30ml)で純アルコール10gです。ロックの場合、さらに少量で純アルコール約10gに達します。
焼酎
焼酎は、1合で純アルコール約20gです。他のお酒と比べてアルコール量が多く、1~2杯飲むだけで翌朝まで運転はできなくなります。
日本酒
日本酒も1合で純アルコール約20gと比較的多くなっています。
チューハイ
チューハイは、アルコール度数7%のレギュラー缶で純アルコール約20gです。他のお酒と比べてアルコール量が少なく思われがちですが、そのようなことはありません。また、何杯も飲む人が多い点にも注意が必要でしょう。翌日の夕方ぐらいまで運転できなくなる場合もあります。
アルコール検査導入にあたっての注意点
緑ナンバーの車を保有する事業所は、安全運転管理者によるアルコール検査が法律で義務付けられています。白ナンバーの車を保有する事業所においても、2022年4月1日より、乗務前後の目視での点呼および酒気帯びのチェック、2023年12月1日からは、アルコールチェッカーによる検査が義務付けられました。アルコール検査を導入する際は、次の2点に注意しましょう。
目視確認の際に前日の飲酒量について確認する(飲酒量と時間も確認)
2022年4月1日から義務化された乗務前後の目視での点呼および酒気帯びのチェックにおいて、目視では飲酒量を把握することが困難なため、前日の飲酒量と飲んだ時間、お酒の種類を確認しましょう。
アルコール検知器の数値を必ず確認する
目視では、酒気帯び状態かどうかは判断できません。必ず、アルコールチェッカーで呼気に含まれるアルコール量を確認しましょう。アルコールチェッカーの中には、クラウド上に記録を保存したり、遠隔地でのチェックができたりするものもあります。
最後に
飲酒後に運転する予定がある場合、どれぐらいでアルコールが抜けるのか気になるでしょう。アルコールが抜けるまでにかかる時間は、体質や体調、体格、性別などさまざまな要素が複雑に絡み合うため、今回ご紹介した計算式だけでは正確な時間を算出できません。
そのため、飲み過ぎた場合は翌日の夕方までは運転しないなど、慎重に行動するべきでしょう。白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化される中、今一度アルコールとの付き合い方を考えてみてはいかがでしょうか。
そのため、飲み過ぎた場合は翌日の夕方までは運転しないなど、慎重に行動するべきでしょう。白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化される中、今一度アルコールとの付き合い方を考えてみてはいかがでしょうか。