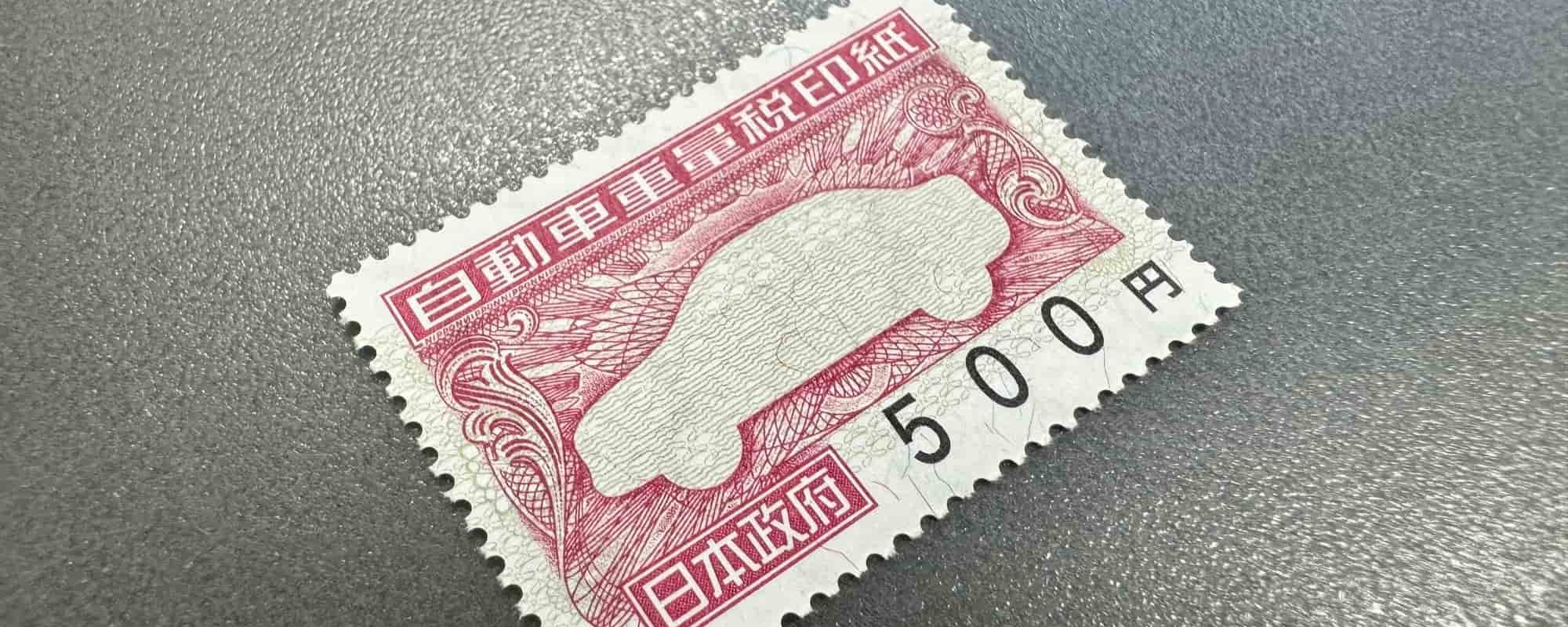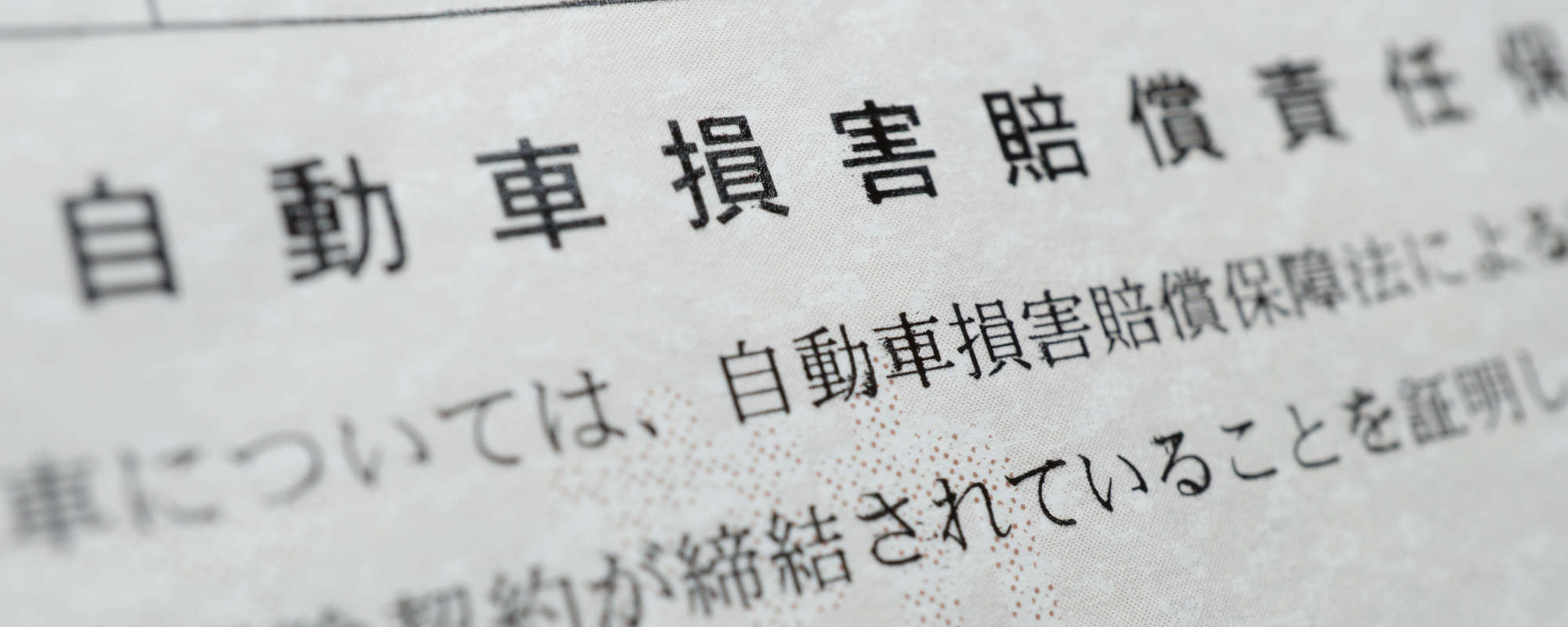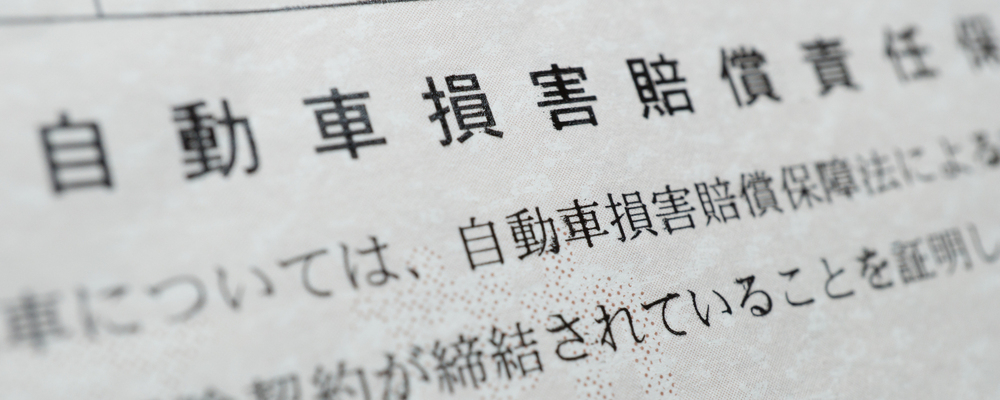ヘッドライトが原因で車検に通らない?2024年の基準の変更点を解説
2024年8月から、車のヘッドライトの車検基準が変更になりました。
これにより、ヘッドライトの状態次第では車検に通らなくなる可能性があるため、注意が必要です。日々のメンテナンスの際に、ヘッドライトの状態が車検適合かどうかを確認してもらいましょう。
この記事では、車検におけるヘッドライトの検査項目と2024年から変更された車検基準について解説。また、車検でヘッドライトが不適合になる理由などについてご紹介します。
これにより、ヘッドライトの状態次第では車検に通らなくなる可能性があるため、注意が必要です。日々のメンテナンスの際に、ヘッドライトの状態が車検適合かどうかを確認してもらいましょう。
この記事では、車検におけるヘッドライトの検査項目と2024年から変更された車検基準について解説。また、車検でヘッドライトが不適合になる理由などについてご紹介します。
カンタン予約・お店で待たない!
車検でチェックされるヘッドライトの3項目

車のヘッドライトは、車検において3つの項目で基準を満たしている必要があります。ここでは、車検でチェックされるヘッドライトの3つの項目について解説します。
光度
ヘッドライトの光度は、車検でチェックされる項目のうちのひとつです。光度とは、光源から特定方向へ放たれる光の明るさを指します。
車検におけるすれ違い用前照灯(ロービーム)の光度の基準値は、片方のヘッドライト1灯につき6,400cd(カンデラ)以上です。検査の際には、ヘッドライトの内部にあるリフレクター(反射板)に反射させた光度を「光度測定点」という基準点で測定します。
車検におけるすれ違い用前照灯(ロービーム)の光度の基準値は、片方のヘッドライト1灯につき6,400cd(カンデラ)以上です。検査の際には、ヘッドライトの内部にあるリフレクター(反射板)に反射させた光度を「光度測定点」という基準点で測定します。
色
車検でチェックされるヘッドライトの項目には、ライトの色も挙げられます。車検に通る色は、原則として白色のみです。ただし、2005年以前に製造された車については、淡黄色も適合となります。
なお、色に関しては、車検において明確な数値基準はありません。ただ、K(ケルビン)で表される色温度でチェックしておくと安心です。
具体的には、4,000~6,000Kが白色の範囲です。この範囲を下回るとヘッドライトの色は黄色く、上回ると青白くなり、いずれも車検に通らない可能性があります。
なお、色に関しては、車検において明確な数値基準はありません。ただ、K(ケルビン)で表される色温度でチェックしておくと安心です。
具体的には、4,000~6,000Kが白色の範囲です。この範囲を下回るとヘッドライトの色は黄色く、上回ると青白くなり、いずれも車検に通らない可能性があります。
光軸
車検でチェックされるヘッドライトの項目のひとつが、光軸です。
光軸とは、ヘッドライトが放つ光の方向のこと。光軸は法律によって、ロービームの光の位置や形についての基準が定められています。
ロービームの光は右上側を暗く、左下側(路肩側)を明るくする「カットオフライン(明瞭境界線)」が設けられており、光が折れ曲がる位置を「エルボー点」と呼びます。エルボー点が規定の範囲内に位置しているかどうかが、ロービームの光軸調整の正確性を判断する基準です。
光軸とは、ヘッドライトが放つ光の方向のこと。光軸は法律によって、ロービームの光の位置や形についての基準が定められています。
ロービームの光は右上側を暗く、左下側(路肩側)を明るくする「カットオフライン(明瞭境界線)」が設けられており、光が折れ曲がる位置を「エルボー点」と呼びます。エルボー点が規定の範囲内に位置しているかどうかが、ロービームの光軸調整の正確性を判断する基準です。
2024年8月にヘッドライトの車検基準は変更されている

ヘッドライトの車検基準については、2024年8月から検査の暫定措置が解除されています。
暫定措置とは、ヘッドライトの検査では「すれ違い用前照灯(ロービーム)の測定が困難な車は走行用前照灯(ハイビーム)でも可」とされていたことです。しかし、街灯の整備や交通量の増大などの交通事情の変化によりハイビームの使用機会が減ったことから、日常で主に使用するロービームを基準とすることになったのです。
1998年9月1日以降に製造された車は、光度や色、光軸について原則としてロービームでの検査となります。なお、1998年8月31日以前に製造された車については、これまで通りハイビームでの検査が行われます。
ちなみに、2024年8月からヘッドライトの車検基準が適用されているのは、北海道、東北、中国地方の各都道府県です。一部その他の地域(関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄)については新基準の導入が延期され、2026年8月1日から実施されることになっています。これは、設備の導入や人材の訓練などに時間がかかることが理由です。
暫定措置とは、ヘッドライトの検査では「すれ違い用前照灯(ロービーム)の測定が困難な車は走行用前照灯(ハイビーム)でも可」とされていたことです。しかし、街灯の整備や交通量の増大などの交通事情の変化によりハイビームの使用機会が減ったことから、日常で主に使用するロービームを基準とすることになったのです。
1998年9月1日以降に製造された車は、光度や色、光軸について原則としてロービームでの検査となります。なお、1998年8月31日以前に製造された車については、これまで通りハイビームでの検査が行われます。
ちなみに、2024年8月からヘッドライトの車検基準が適用されているのは、北海道、東北、中国地方の各都道府県です。一部その他の地域(関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄)については新基準の導入が延期され、2026年8月1日から実施されることになっています。これは、設備の導入や人材の訓練などに時間がかかることが理由です。
車検でヘッドライトが不適合になる理由

ヘッドライトが原因で車検に不適合になるのは、どのような場合なのでしょうか。ここでは、車検でヘッドライトが不適合になる理由について解説します。
光度が不十分
ヘッドライトの光度が不十分だと、車検で不適合になる可能性があります。測定点における光度が、1灯につき6,400cd以上という基準を満たさないヘッドライトは、車検不適合となります。
ヘッドライトがくもっていたり、ヘッドライトバルブ(電球部分)が劣化していたりする場合、光度不足が起きやすくなります。また、HIDヘッドライトの不具合は、ユニット交換などの場合、高額な修理費用がかかることがあるので注意が必要です。
また、バッテリーやオルタネーターなどに問題を抱えていると、光度が不足する場合もあります。
ヘッドライトがくもっていたり、ヘッドライトバルブ(電球部分)が劣化していたりする場合、光度不足が起きやすくなります。また、HIDヘッドライトの不具合は、ユニット交換などの場合、高額な修理費用がかかることがあるので注意が必要です。
また、バッテリーやオルタネーターなどに問題を抱えていると、光度が不足する場合もあります。
ヘッドライトバルブの色が白くない
ヘッドライトバルブに不具合があったり、青白く光る社外品に交換していたりといった理由で、照射光の色が白くないと、車検で不適合になる可能性が高くなるでしょう。
また、ヘッドライトの左右で色味が違うのも、車検に通らない原因となります。
また、ヘッドライトの左右で色味が違うのも、車検に通らない原因となります。
光軸が基準の範囲内に収まっていない
ヘッドライトの光軸が適切な範囲内になっていない場合、車検に通らない可能性が高まるので注意が必要です。
光軸は走行中の振動や衝撃、または社外品交換時の調整不足・車高の変更などによって、ずれることがあります。上向きにずれていると対向車を眩惑(げんわく)させるため、たいへん危険です。また、下向きにずれていると夜間走行時に前方を正しく照らせないので、安全運転に支障をきたしかねません。
光軸は走行中の振動や衝撃、または社外品交換時の調整不足・車高の変更などによって、ずれることがあります。上向きにずれていると対向車を眩惑(げんわく)させるため、たいへん危険です。また、下向きにずれていると夜間走行時に前方を正しく照らせないので、安全運転に支障をきたしかねません。
ヘッドライトのせいで車検不適合にならないようにするための方法

ヘッドライトが原因で車検に通らないという事態を避けるには、どのようにしたらいいのでしょうか。ここでは、ヘッドライトのせいで車検不適合にならないようにするための方法について解説します。
ヘッドライトの黄ばみを除去する
ヘッドライトの黄ばみは、車検不適合の原因になりかねません。リスクを避けるため、黄ばみを車検前に除去しておきましょう。
ヘッドライト表面はカー用品店などで販売している専用クリーナーなどで磨くことで、きれいに除去できます。しかし、DIYでは効果が長持ちしなかったり、ボディに傷が付いたりする可能性もあるため、オートバックスなどでプロの整備スタッフに作業を依頼するのが確実です。
ヘッドライト表面はカー用品店などで販売している専用クリーナーなどで磨くことで、きれいに除去できます。しかし、DIYでは効果が長持ちしなかったり、ボディに傷が付いたりする可能性もあるため、オートバックスなどでプロの整備スタッフに作業を依頼するのが確実です。
ヘッドライトバルブを交換する
ヘッドライトの電球部分であるバルブを交換するのも、光度不足による車検不適合回避の方法です。バルブ交換の際には、純正品または「車検対応」と書かれたものを選びましょう。また、左右セットで交換するのが基本です。
バルブはDIYでも交換作業は可能ですが、光軸がずれるリスクを伴います。バルブの交換作業は光軸調整も含め、プロの整備スタッフに任せるのが安心といえます。
バルブはDIYでも交換作業は可能ですが、光軸がずれるリスクを伴います。バルブの交換作業は光軸調整も含め、プロの整備スタッフに任せるのが安心といえます。
ヘッドライトテスターで光軸調整をしてもらう
ヘッドライトの光軸が原因で車検不適合にならないようにするため、「ヘッドライトテスター」という機器で光軸の調整をしてもらうのがおすすめです。ヘッドライトテスターとは、車のヘッドライトの光度や光軸を計測し、合否判定するものです。
なお、ヘッドライトテスターは車検の検査場だけでなく、カーディーラーやカー用品店の指定整備工場などにも設置されています。光軸が適切かどうか不安な場合は、日々のメンテナンスのついでにチェックしてもらうといいでしょう。
なお、ユーザー車検前の光軸調整のみの依頼は、店舗によっては断られる可能性があります。
なお、ヘッドライトテスターは車検の検査場だけでなく、カーディーラーやカー用品店の指定整備工場などにも設置されています。光軸が適切かどうか不安な場合は、日々のメンテナンスのついでにチェックしてもらうといいでしょう。
なお、ユーザー車検前の光軸調整のみの依頼は、店舗によっては断られる可能性があります。
オートレベライザーをチェックしてもらう
ヘッドライトの光軸のせいで車検不適合になるリスクを避ける方法として、「オートレベライザー」を事前にチェックしてもらうことが挙げられます。オートレベライザーとは、車に乗る人の人数や荷物の量によって車の姿勢が上向きになったとき、自動でヘッドライトの照射方向を下げるといった調整機能です。
オートレベライザーに不具合があると、光軸が上下することがあります。プロの整備スタッフにチェックしてもらい、場合によってはリセットしてもらうなどの調整作業を依頼しましょう。
オートレベライザーに不具合があると、光軸が上下することがあります。プロの整備スタッフにチェックしてもらい、場合によってはリセットしてもらうなどの調整作業を依頼しましょう。
社外品の場合は点検・交換も視野に入れる
ヘッドライトを純正品から社外品に交換している場合、色味や明るさによっては車検不適合になる可能性もあります。また、DIYで交換したヘッドライトは光軸がずれていることも考えられます。
車検対策として、社外品装着の場合は事前に点検を行い、プロの整備スタッフに光度や色味、光軸などをチェックしてもらいましょう。「車検対応」と記載された製品でも、車体側に問題がある可能性も捨てきれないからです。車検非対応のヘッドライトを装着している場合は、必ず交換するようにしてください。
車検対策として、社外品装着の場合は事前に点検を行い、プロの整備スタッフに光度や色味、光軸などをチェックしてもらいましょう。「車検対応」と記載された製品でも、車体側に問題がある可能性も捨てきれないからです。車検非対応のヘッドライトを装着している場合は、必ず交換するようにしてください。
車検前のヘッドライトチェックはオートバックスへ

ヘッドライトの車検基準変更に備えて、車検前のチェックは欠かせません。ヘッドライトの光度や色、光軸はプロの整備スタッフにより、ヘッドライトテスターを使って確認してもらう必要があります。信頼できる業者に相談をして、日々のメンテナンスの中での点検や、早めの車検予約を行いましょう。
オートバックスでは、車検の早期予約やアプリ会員向けの割引サービスなどが利用できるため、お得に車検を受けられます。さらに、オートバックス車検を受けた方限定で、24時間対応のロードサービスである「オートバックス安心いつでも補償」にも加入可能です。
オートバックスの車検実績は全国累計1,000万台以上!「車検が切れてしまった車を所有している」「車検の期限が迫っているけれど、受ける場所を決めていない」という方は、豊富な実績で安心なオートバックスをぜひご活用ください。
なお、車検の予約は一部店舗では承っておりません。依頼をご検討の際には、ご希望の店舗までお問い合わせください。車検予約の上、オートバックスへのご来店をお待ちしております。
オートバックスでは、車検の早期予約やアプリ会員向けの割引サービスなどが利用できるため、お得に車検を受けられます。さらに、オートバックス車検を受けた方限定で、24時間対応のロードサービスである「オートバックス安心いつでも補償」にも加入可能です。
オートバックスの車検実績は全国累計1,000万台以上!「車検が切れてしまった車を所有している」「車検の期限が迫っているけれど、受ける場所を決めていない」という方は、豊富な実績で安心なオートバックスをぜひご活用ください。
なお、車検の予約は一部店舗では承っておりません。依頼をご検討の際には、ご希望の店舗までお問い合わせください。車検予約の上、オートバックスへのご来店をお待ちしております。